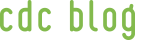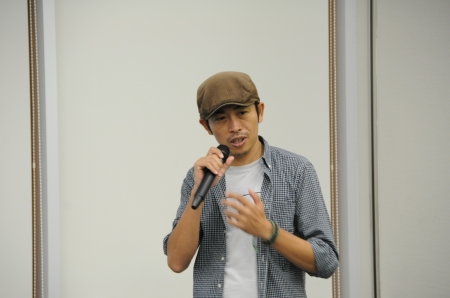新年あけましておめでとうございます!
みなさま大変ごぶさたしております
ブログの更新が遅いヤキュージョーです

本年もどうぞよろしくおねがいします
さてさて、昨年秋から年末までの報告を一挙に
石田さんは自転車で世界一周をされた経験を持ち現在でも様々な場所へ自転車で旅をしてそのエッセイなどを書かれています

和歌山県の白浜で生まれ育った石田さんは、子供のころ見た自転車旅行者に憧れていたそうです
そして和歌山県一周をはじめに近畿一周そして大学生の時に日本一周を達成します
大企業への就職から世界旅行の決断など、旅の途中でも様々な葛藤があったようです
悩んだときはいつも後悔しない方を選んできたと言います

7年間で95000km 87か国に及ぶ行程をきれいな景勝地の写真を見せていただきながら解説していただき、笑いあり涙ありのトークイベントになりました
そして翌月11月はジェンダー論や美術教育に詳しい大野左紀子さんに「図工の時間は楽しかったですか」というタイトルで我々が受けてきた美術の教育のありかたについてお話ししていただきました。

大野さんは芸大を卒業して20年間作家としても活動をされながら同時に様々な業界の人にデッサンを教えるなど美術教育にも長年携わっています、現在は名古屋芸大の非常勤されています
ご自身の著作「アーティスト症候群」「アート・ヒステリー」については、世の中には様々な水準の美術の世界があって、そこでアートというものについていままで語られていなかった切り口で語りたかった。業界向けやアートって面白いですよというものではなく、そこから漏れ出てくるモヤモヤとした事柄についてまとめてみたかったというのがきっかけのようです。

さて、本題ですが大野さんは明治から始まった主観中心の作文の型に着目します。
それは全く客観性が問われないものだったようで、日本の美術教育にもこの主観中心の考え方が適応されてきたため、その後も大きな影響を残し続けているといいます
子供たちに「感じたままやりなさい」というのは無責任で、個性だとか人格形成とか内面の心の問題に踏み込まずにもっと客観的な視点を持てるような教科内容を作るべきと大野さん
最近の大野さんが接した例では美大の学生は自分の作品を全く説明できない学生が増えていることに警鐘を鳴らします
ただこの問題も「個性が大事、自由に描いてみなさい」という学校教育の中での教え方が一つの要因になっているといいます

現在作家を目指して活動している学生に対しては、長い歴史のなかで培われたテクニック、方法論を知ることで表現をより自分のものにして欲しいと作家を続けながら美術教育に携わってきた大野さんならではの大変説得力のあるお話しでした

そして12月にはかわぐち社会科見学部で最強の鉄球を作る工場としてテレビでも同じみの本町にある富和鋳造さんにお邪魔しました。

工場内ではたくさんの職人さんが作業をされていました。忙しい合間にもとても丁寧に説明していただきました。これが例の「最強の鉄球」ですね

細かい金属片などをまとめて溶かす溶鉱炉のようなところ、もちろん熱いです

職人さんたちは溶けた鉄を「湯(ゆ)」と呼んでいます。いままさに湯が型に注がれようとする瞬間です。
なぜ鋳物職人になったのですか?という質問に対して「最後までどんなものができるかわからない」ところと仰っていて、「どんなに難しい注文にも応える努力を惜しまない。またうまくできた時は大きな充実感が得られる」と自分の職業に誇りをもって取り組んでいる様子がわかりました

これからも川口から質の良い製品を世界中に届けてほしいですね
ということで今年もたくさんの企画を用意しておりますのでお楽しみに!
では